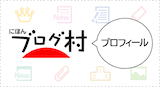受験英語には、たくさんの山場があります。
単語・熟語の暗記にはじまり、難解な英文法、リスニングにライティングと、受験生は多くの山を越えていかなければなりません。
その中で、最も大きな山場が長文読解(リーディング)ではないでしょうか。
ボク自身高校生のときに、この山場でつまづいた一人です。長文読解でつまづいてしまい、英語自体に苦手意識を持つようになってしまいました。
この記事ではそんな自分の体験や反省をもとに、長文読解を得意にするための勉強法について、3ステップに分けて説明しようと思います。
各ステップごとにおすすめの参考書(問題集)についても紹介しています。
おすすめの参考書(問題集)についてはわかりやすさだけでなく、3ステップ通して無理なく学べるように「コンパクトであること」を重視して選んでみました。
あなたの学習プランに合わせて、必要な部分を参考にしてもらえるとうれしいです。
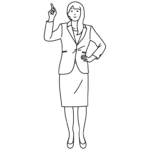 アシスタント
アシスタントこの記事は、次のような方におすすめです。
- これから長文読解の勉強に入るので、勉強法を知りたい。
- 長文読解に最適な参考書・問題集を知りたい。
- 長文読解を得意にするコツを知りたい。
- 長文を読む正確さだけではなく、スピードも上げたい。
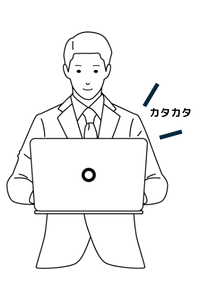

この記事を書いた人
ヒラク
TOMOSU BLOG 運営者・執筆者
早稲田大学政治経済学部政治学科卒 / 早稲田5学部・上智3学部を受験し、すべて合格
なぜ長文読解が伸びないの?その理由を分析!
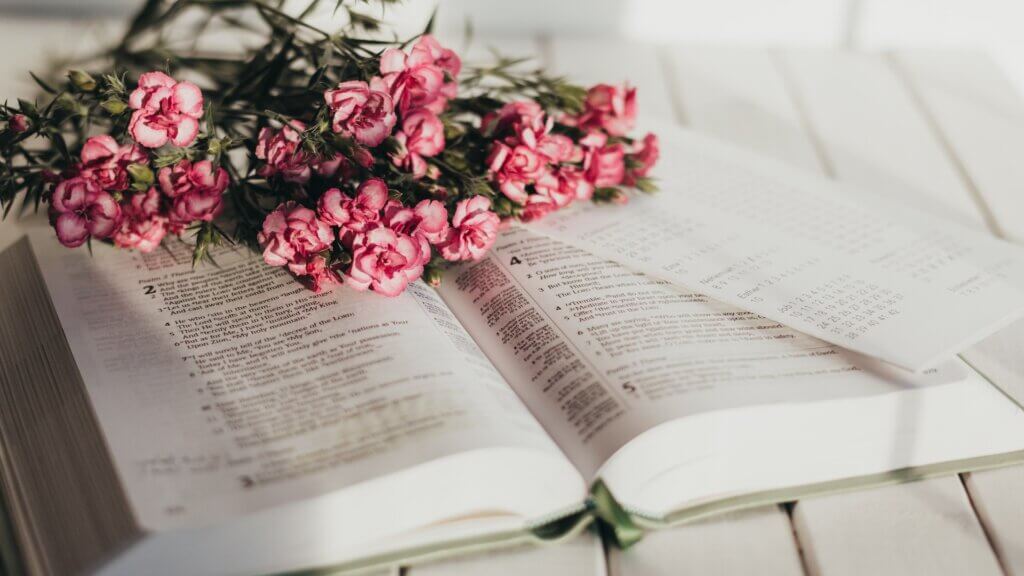

なぜ、長文読解のスキルが伸びないのか?苦手なのか?ボクは次の3つが原因だと思います。
土台ができていない
長文が苦手だという前に、考えてほしいのが「土台を固められているかどうか」です。
ボクの思う、長文読解に必要な「土台」とは①単語・熟語(ボキャブラリー)、②構文力の2つです。
この2つに共通するのは、「英語をミクロレベルで理解する力」ということになります。
英語という言葉を細かくしていったときに、最も細かい要素が①単語・熟語です。そして次に細かい要素が②構文です。
まずは英文をミクロレベルで理解する力を備えたうえで、長文というマクロレベルに取り組むべきです。
ミクロの土台ができていないのに、マクロに挑んだって無茶ですよね。
あなたがもし、基礎に自信がないというのであれば、まずはこの2つに重点を置いて学習を進めましょう。
長文読解に必要な学習ステップを理解していない
2つ目に考えられるのが、「長文読解に必要な学習ステップを理解していない」ということです。
ボク自身も、高校生の時はこの学習ステップを理解していなかったために、成績がまったく伸びませんでした。
「長文なんて、単語さえ覚えれば勝手に読めるようになるだろう」という程度の認識しかありませんでした。
授業には欠かさず出席していましたが、その程度の認識で読解力が上がるわけないですよね。
今振り返って思うと、英語担当の先生もそのあたりのことを深く理解していなかったように思います。
ただ長文を読ませる、問題を解かせるの繰り返しでした。
予備校ではこの読解力を上げるためのステップを講師の方がしっかりと説明し、実践してくれました。
今回の記事で、この学習ステップについて詳しく解説したいと思います。
「リスニング」「ライティング」に時間をとられている
3つ目に考えられるのが、「『リスニング』『ライティング』に時間をとられてしまっている」ことです。
ボクは個人的にですが、「読む」ことができれば、ある程度「聴く」「書く」といったことはできると思っています。つまり、「読む」がベースなのです。
「読む」ことを通じて、英語の言葉の並びやルールを知ることで、「耳で聴いた」ときに英単語の並びが頭に浮かびますし、「自分で書く」ときでも、どういう順番で言葉を組み立てていけばよいかがわかります。
最近の大学受験は、「リスニング」と「ライティング」の割合が増えましたよね。
多くの受験生が、その対策として①「聴く」「書く」に時間をかけていると思うのですが、その結果として②「読む」にかける時間が減る→③「読む」という土台が不安定→④「読む」「聴く」「書く」すべてが伸びない、という悪循環になってしまっていると思うのです。
ですので、まずは「読む」ことを通じて、英語のルールをしっかりと身につけることが大切だと思います。
長文読解ステップ① 構文解釈力を身につける


ステップ①は、構文の理解です。
英文には次の5つのタイプがあります。
| パターン | 構造 | 例 : 訳 |
| 第1文型 | SV | He cried. :彼は泣いた。 |
| 第2文型 | SVC | She looks so sad. :彼女はとても悲しそうだ。 |
| 第3文型 | SVO | He plays baseball. :彼は野球をしている。 |
| 第4文型 | SVOO | My parents bought me a new book. :両親が新しい本を買ってくれた。 |
| 第5文型 | SVOC | My mother always keeps the kitchen clean. :母はいつも台所をきれいにしている。 |
なぜ構文をとる必要があるのかというと、英語の「動詞」が5文型のうちどのタイプになるのかによって意味が決まること、文の要素とそれ以外を分けることで意味が分かりやすくなることなどがあげられます。
もし、あなたがまだ構文をとれないのであれば、何を言ってるのかわからないかもしれません。
現時点では、ひとつひとつの文章をタイプ分けすることで、その文の意味を正確に理解できるということだけわかってください。
そして、はじめのうちは構文を詳しく解説してくれる講座や参考書を使って、構文解釈の基本を学びましょう。
ここでポイントとなるのは、この段階では「問題を解く」ことは重視しないということです。
問題を解いて、間違いが多くてもこの段階では気にする必要はありません。とにかく構文をとって、訳を正確に導き出すことに重心を置いてやっていきましょう。
そして、なかなか正確に構文をとることができなくても気にしないでください。
ボクも最初はたくさん間違えましたが、受験直前には、英文を見ただけで、構文が浮き上がって見えてくるようになりました。
あなたもきっと大丈夫ですので、この段階では少なくとも1週間に1本の長文の構文をとるようにしてください。
長文読解ステップ② 英文のルールを学ぶ


5文型をおおよそ見分けられるようになったら、次に学習すべきなのが、英文読解のルールを知るということです。
これもジャンルとしては「構文」になりますが、構文の中でも、より応用的な部分と言えるでしょう。
英文読解のルールとは、例えば「前置詞のついていない名詞は必ず文の要素(S、O、C)になる」とか「形容詞は①名詞にかかる、②Cになる、の2パターン」といったような、文を読む上での原則のことです。
英語という言葉は、ルールがキッチリ決まった言葉です。日本語のようにおおらかな言葉ではありません。
書き手が一定のルールに基づいて書いているわけですから、それを受け取る側もそのルールを理解しておかなければ、コミュニケーションは成立しません。
裏を返せば、このルールさえしっかり理解すれば、それぞれの文を文脈や流れに頼ることなく訳すことができるのです。
よく、意味が分からない文を「文脈で理解する」「行間を読む」という方法に頼る人がいますが、それは間違いです。
そのような人は、いわば「たまたま読めている」だけなのです。
「文脈」や「行間」に頼らず、もっと言えば背景知識が何もなかったとしても長文を読める、それが本当の英語力です。
ですので英文読解のルールを知ることによって、どのような文であっても正確に読み解くということを目標にしましょう。
この段階でも、「問題を解く」ということよりも「英文を読む」ということに重心を置いてください。
※構文学習については以下の記事に詳しくまとめています。
長文読解ステップ③ 問題を解く力をつける


ステップ③がいよいよ問題を解く力をつける段階となります。
上で説明したステップ①、②の基礎段階をしっかりと踏み、同時に単語や文法なども固めている受験生であればインプットは大丈夫なので、このステップ③でアウトプットに取り組むことになります。
この段階にきて、はじめて「解く」ということに重点を置くわけです。
ここでいきなり過去問に入る人もいるかもしれませんが、ボクは個人的にはおすすめしません。
なぜなら、過去問よりも問題集のほうが解答・解説が充実しているからです。
過去問の解答・解説は必要最低限しかのっていないものが多いように思います。
それに比べて、問題集は正解だけでなく、問題を解く際の注意点や不正解の選択肢について「なぜこれが不正解なのか」といった点も説明しているものが多いからです。
ですので応用に入っていきなり過去問演習に進むのではなく、まずは問題集で「問題を解く力」をつけましょう。
なお、「解く」段階であっても、問題を解き終わった後に、知らない単語を調べる・構文をとるといったことはしっかりとやりましょう。解きっぱなしで終わってると力が伸びません。
長文読解ステップ①~③の英文を音読することで効果倍増!
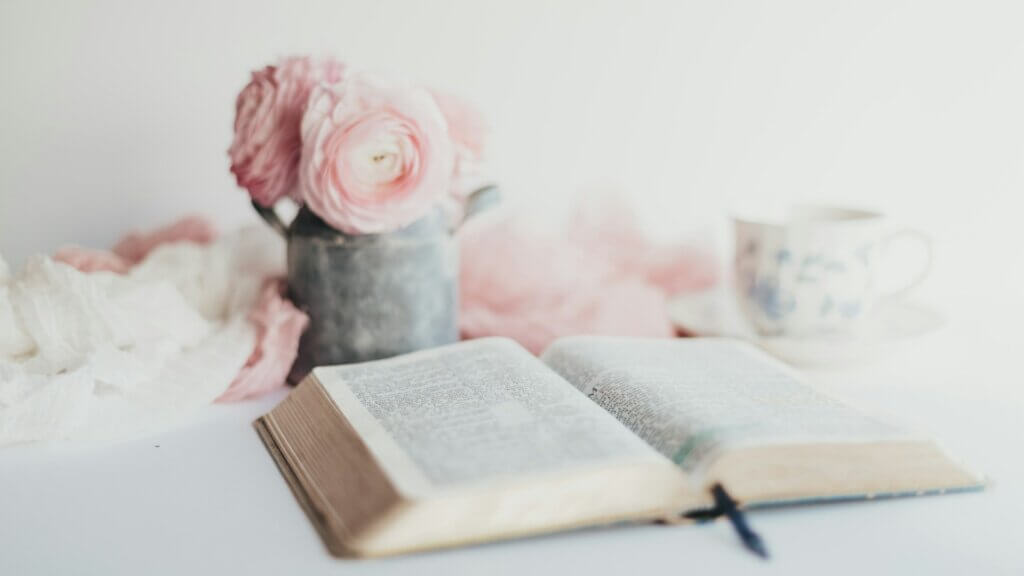

さて、ここまで長文読解の学習法を3ステップにわけて紹介しました。そして、各ステップの学習と同時並行でやってもらいたいのが「音読」です。
各ステップごとに構文解釈も終わり、問題も解き、解説まで読み終えたテキストや参考書を「声に出して読む」のです。
最近でこそ、色々な参考書に「音読」の有用性が当たり前に書かれるようになりましたが、ボクの受験生時代にはまだ音読というのはマイナーな勉強法でした。
ボクは第1志望であった早稲田大学に合格できた大きな要因のひとつが、「英語の音読」のおかげだと思っています。
それほど、音読の効果は抜群でした。
音読の効果としては何と言っても、「英語を英語として理解できるようになる」ことです。
学習初期の頃は頭の中で「英語を読む→日本語に訳す→意味を理解する」だったのが、音読を続けることによって「英語を読む→意味を理解する」に変化します。
日本語に訳すというプロセスがなくなった分、読解スピードがグンとあがります。
音読を通じて英文を日常的に「浴びる」ことによって、頭が「英語脳」になっていくのです。
上で、順番として「英文のルールを学ぶ」ことよりも先に「構文解釈力を身につける」ことを置いたのも、早く音読に入れるようにするためです。
音読を効果的に行うには、構文をとっておかないといけないのでそのような順番にしました。
初めのうちはあなたのできる範囲で構わないので、英文を「日本語に置き換えずに」理解していくことを意識して読んでみてください。
※下の記事にて音読の効果的なやり方を紹介しています。
長文読解の勉強におすすめの参考書
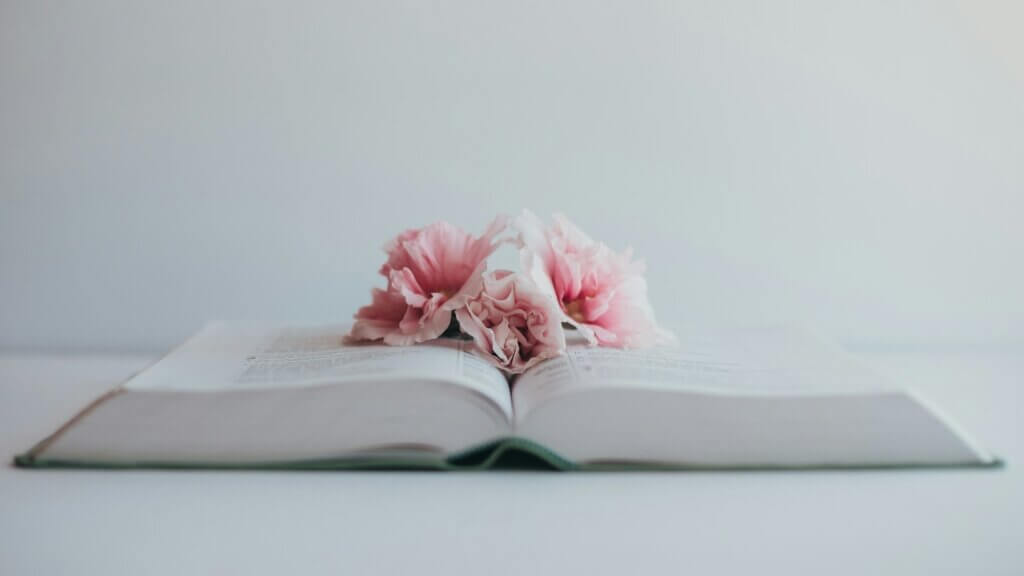

ステップ①におすすめの参考書 『こう読みこう解く英文読解 (河合塾シリーズ)』
長文読解の基礎である「構文」。
この『こう読みこう解く英文読解 (河合塾シリーズ)』は、その構文の中でも5文型の理解に重心を置いている、いわば“構文の基本書”。
決してメジャーな参考書ではないかもしれないが、amazonのレビューでは評価が高く、「隠れた名著」というクチコミもある。
ボク自身も内容を確認してみたけれど、長文読解の入門書としてかなりおすすめ。
河合塾が出版している参考書は、「メジャーではないけど質が高い」というのがボクの印象。
ステップ②におすすめの参考書 『新版 富田の英文読解100の原則』
ボクが実際に受験生時代に使用した参考書。社会人になってからも再度使用したほど信頼している1冊。
5文型の知識をもとに、それに付随したルールを学ぶことができる。
本書での学習後、読解力が飛躍的に上がり、早稲田大学合格につながった。
解説の分量が多く、なかなかハードな部分もあるが、本気で取り組めばこれほど効果的な参考書はないと思う。
あなたが本気で読解力をあげたいなら、ぜひ手にとってみてほしい。
ステップ③におすすめの参考書 『関正生のThe Rules英語長文問題集』
スタサプの英語講師・関正生先生の長文問題集『関正生のThe Rules英語長文問題集』。
掲載されているすべての長文に構文解説がついているのがうれしいポイント。
難易度別に4冊に分かれているので、自分の志望校レベルに合わせて1・2冊程度こなすと良いと思う。
関先生の解説は、難しい表現を避けて本質的な部分にだけ焦点を当てているのが印象的。
本書で長文読解の「質」を上げた後に、過去問で「量」をこなすのがおすすめ。
まとめ:長文読解は階段を1段ずつ
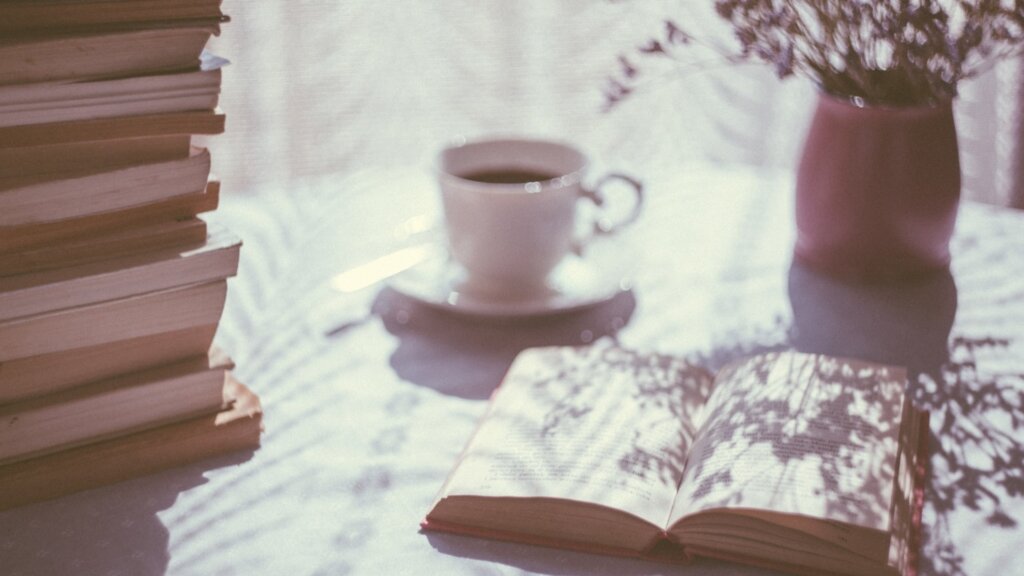

いかがだったでしょうか。
書店をめぐって、いろいろな参考書を手にとってみましたが、自分が愛用していた富田先生のものと、スタサプでおなじみの関先生のものが頭ひとつ抜けて質が高いように感じました。
解説を見る限り、初学者の方は、関先生の参考書の方がなじみやすいかもしれません。
難関大学を志望している受験生には、富田先生の参考書にはぜひ1度、目を通してもらいたいと思います。
ボク自身はこのステップ①~③のプロセスで、長文読解を得意分野にすることができました。
そして、この学習ステップを焦らずに1段ずつしっかりと登ったことが成績アップにつながったと思っています。
大事なことは、ステップ①・②を固めてからステップ③に移るということです。
成績が伸び悩む人は必ずと言っていいほど、アウトプットを早くしたがります。しかし、しっかりとしたインプットを経なければ、アウトプットの作業は意味がないのです。
焦る必要はありませんから、まずはじっくりと基礎を固めることに集中してください。
それぞれの段階をしっかりと固めていったあなたは、その効果の大きさを実感できるはずです。
大事なのは「継続すること」。膨大な量の長文に取り組む必要はありません。
自分の学習プランに合わせて、受験直前まで無理なく続けることを意識して取り組んでみてください。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。